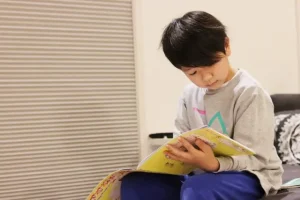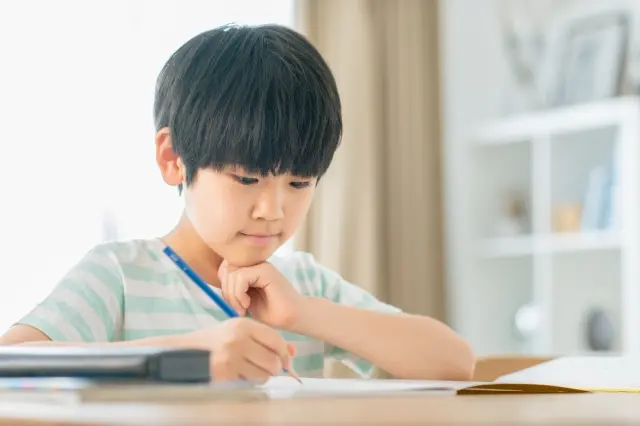
「何度書いても英単語が覚えられない」「すぐに忘れてしまう」「スペルをすぐに間違える」。
小学生の英単語学習でよく聞かれる悩みです。保護者としても「どう覚えさせるのが正解?」「やっぱり書いて覚える練習を繰り返すべき?」と迷うことがあるかもしれません。
しかし、英単語は「ただ覚えればいい」ものではなく、「覚える順番」や「覚え方のステップ」を間違えると、どれだけ時間をかけても定着しにくくなります。
実は、小学生の英単語学習には“効果が出やすいタイミング”と“やってはいけない覚え方”が存在します。
この記事では、
- 小学生が英単語を覚えられない原因
- 学年別に効果の出やすい覚え方
- 覚えた単語を定着させる工夫
- スペルが苦手な子でも取り組みやすいステップ
- 家庭学習でよくある失敗のパターン
などをわかりやすく整理し、「この順番で進めれば大丈夫」という学習ステップを解説していきます。
「うちの子に合った方法で、楽しみながら英単語を覚えさせたい」「中学英語でつまずかない土台を作りたい」という方にとって、役立つ指針になるはずです。
それではまず、「なぜ小学生でも英単語学習を始めておくべきなのか」から見ていきましょう。
小学生の英単語学習はなぜ必要?中学進学で差がつく理由
「英単語は中学に入ってから覚えればいいのでは?」と思われることもあります。
しかし、実際には小学生の段階で英語に触れているかどうかによって、中学のスタート時点で大きな差がつき始めます。
ここでは、小学生のうちに英単語に触れておくことがなぜ有利になるのかを整理してみましょう。
中学英語は「単語がわからない=授業が理解できない」構造になっている
中学1年生の英語はスピードが速く、授業も「意味を理解して進む」ことが前提になります。
そのため、次のような状態になると授業への抵抗感が高まります。
- 知らない単語が多くて、文の意味がわからない
- 意味が取れないため文法説明が頭に入らない
- 音読ができず、読むこと自体に時間がかかる
英単語の基礎的な理解があるだけで、この「理解できない不安」から守られやすくなります。
「音で知っている単語」があるだけで読みやすさが変わる
単語は「書けるかどうか」ではなく、「音として聞きなれたものがあるかどうか」で理解スピードが変わります。
小学生のうちに触れている単語があると、
- “見た瞬間に読める”
- “なんとなく意味がわかる”
- “文章全体を理解しやすい”
という状態を作りやすくなります。
これが「英語=わかるもの」という認識につながります。
「知っている英単語がある」→「読むのが怖くない」という安心感に直結する
中学英語でつまずく子の多くは、「読めない」「意味が取れない」という恐怖心から英語そのものを拒否してしまうケースが目立ちます。
一方、小学生のうちに
- りんご=apple
- 犬=dog
- 好き=I like …
といった“知っている単語”が増えると、教科書の文章に「見覚えのある単語」が混ざるため、読むことへの心理的ハードルが下がります。
「英単語の読み方」→「スペルへの理解」へとつながる
英単語を音として知っている状態で、「文字はこう書くんだ」と理解できると、スペル学習への抵抗が少なくなります。
特にフォニックス(音と文字の関係)を知ることで、「わからない文字の羅列」ではなく「法則をもった単語」として捉えられるようになります。
早期学習の目的は「暗記」ではなく「慣れ」と「抵抗をなくすこと」
小学生から単語を覚える目的は、「中学のために先取りしておくこと」ではなく、「英語に触れることへのストレスをなくしておくこと」にあります。
英単語への慣れがあると、中学英語を「知らないことを教わる時間」ではなく「知っていることを広げる時間」として受け止めやすくなります。
このように、小学生の英単語学習は「競争のための先取り」ではなく、「英語を嫌いにならない土台をつくるもの」と考えることが大切です。
英単語を覚える前に整えておきたい基礎準備
英単語がなかなか覚えられない原因は、「記憶力が弱いから」ではありません。多くの場合、「覚える前の土台」が十分に整っていないために、無理に暗記しようとして挫折するケースがほとんどです。
ここでは、英単語学習の成功に必要な“3つの準備”を整理します。
「音を聞く」「口にする」経験があるかどうか
英単語は、頭の中で音と意味がつながっている状態のほうが覚えやすくなります。
言えない単語を書いて覚えるのは、砂の上に文字を書くようなものです。
例:「dog」は「ディー・オー・ジー」ではなく、「ドッグ」という音で認識されている状態が理想です。
先にやるべきこと
- 英単語を「聞く」ことから始める
- 声に出す練習も取り入れる
- 正しさより「自分で言える」ことを優先する
「単語の意味がイメージできる」状態を作る
意味がイメージできる単語は、暗記ではなく“理解によって記憶される”ため、忘れにくくなります。
たとえば以下のようなステップが効果的です。
- apple → りんごの写真や実物と結びつける
- run → 映像や動作と関連づける
- happy → 表情や雰囲気で感じ取らせる
文字に進む前に「視覚・動作・感情」を絡めることで定着しやすくなります。
「間違えてもいい」という安心感を与える
覚えたての英単語を口に出したとき、「違うよ」「正しく言って」と繰り返されると、反射的に口が閉ざされます。
英単語学習に限らず、語学は「言ってみた」という行動そのものが第一歩です。
- 間違いを指摘する前に「言えたこと」を認める
- 「惜しい!もうちょっとで正解だね」という伝え方をする
- 「発音が100点になる必要はない」という前提を作る
心の安全を確保できると、英単語を口に出す回数が増え、結果として覚えやすくなります。
「覚える」前に「言える・イメージできる」状態があると定着率は一気に上がる
小学生の英単語学習は、「文字の暗記」から始めるのではなく、「音→意味→文字」の順番で学ぶことで、学習効率が高くなります。
この流れが整っているかどうかで、暗記への負担が大きく変わってきます。
小学生に合った英単語の覚え方|学習ステップとコツ
英単語を覚えるとき、多くの子どもがつまずくのは「覚える順番」が間違っているからです。
特に、小学生の段階で「書いて覚える方法」から始めてしまうと、苦手意識が一気に高まります。
ここでは、小学生に無理なく定着しやすい英単語の覚え方を、4つのステップに分けて紹介します。
ステップ1|音で覚える(聞いて→まねして言ってみる)
最初の段階では、スペルや意味を覚える必要はありません。まずは「音で知っている単語」を増やしていきます。
- 英語の歌やチャンツを使って口に出す
- 短いフレーズを繰り返す(I like ○○. / This is my ~.など)
- 動画やアニメ英語でもOK
「言える単語=覚えやすい単語」です。
ステップ2|意味と結びつける(イメージとリンク)
音がわかってきたら、「これはこういう意味だよ」と視覚や感覚を通して理解させます。
- りんご=appleをイラストや実物で示す
- 走る=runは動作で表す
- happy=表情カードでイメージさせる
意味がつかめると、記憶が自然に固定されます。
ステップ3|文字に触れる(読む→パターンに気づく)
音と意味が結びついた段階で初めて「文字」を導入します。このとき、「書く」前に「読めること」を優先します。
- フォニックスで音と文字の関係を学ぶ
- 単語を見せて「これは〇〇だったよね」と確認
- 「言える単語=読める単語」にしていく
「読みやすくなった」=「スペルを理解しやすくなる」状態です。
ステップ4|書く・使う(アウトプットで定着)
読み方と意味がわかってきたら、「書く・使う」を入れます。ここでは“いきなり丸暗記する”のではなく、“言える文を少しずつ書く”流れが効果的です。
- 1単語ずつではなく、短文で覚える(I like dogs.など)
- 書く練習は「言えるもの」だけに限定する
- 簡単なクイズやゲーム形式で復習する
この段階では「正確に覚えること」より、「意味を理解したまま形にできること」が重要です。
「音→意味→読み→書く」の順序を守ると、覚えるスピードと定着率が上がる
小学生のうちは、この流れが自然に身についていくことで、「英単語=覚えるのがつらいもの」ではなく、「知っている言葉が増える楽しさ」へと変わっていきます。
楽しく続けられる英単語学習法|アプリ・教材・家庭での工夫
英単語学習は「覚え方」と同じくらい「続け方」が大切です。どれだけ良い方法でも、子どもが苦痛を感じてしまえば長続きしません。特に小学生の場合、「楽しい」「できた」「もっとやってみたい」という感覚が継続のカギになります。
以下では、学習スタイルに合わせて取り入れやすい方法をタイプ別に紹介します。
①リズム派の子に合う|チャンツ・歌・リピート型アプリ
音やリズムに敏感な子は、チャンツや音声アプリで口に出す学習スタイルが効果的です。
例)
- 同じ英単語をリズムに合わせて連呼するアプリ
- 「言えたらOK」というクイズ型リピート練習
- 歌詞に単語が含まれた音源学習
「歌える=覚えている」ではありませんが、「音として記憶される」きっかけになります。
②イメージ型の子には|イラスト・実物リンク型教材
意味と映像を結びつけることで記憶がスムーズに残るタイプの子は、「単語+絵カード」や「写真付き教材」が向いています。
- 「apple」と書かれたカードだけでなく、りんごのイラストカードを使う
- 日常のものでカテゴリ学習(food / animals / school items など)
- 「連想ゲーム」や「あてっこクイズ」にすることで記憶が強まります
③文章で覚えるのが得意な子には|短文ごと覚える学習法
単語だけではなく「文の中で覚えるほうがわかりやすい」子どもには、短い文をまるごと覚える方法が効果的です。
例)
- 「I like cats.」→like、catsが自然に入る
- 「This is my bag.」→my、bagの意味も理解しやすい
文脈を通すことで、単語単体よりも理解が深くなります。
④ゲーム感覚がモチベーションになる子には|親子で対戦型
競争やクイズが好きな子には、家庭で次のような遊びを取り入れると効果的です。
- 「先に言えたほうが勝ち」単語バトル
- 「意味をジェスチャーで当てる」英語あてゲーム
- 読み札を英語にした“英単語かるた”風遊び
「遊んでいるつもりで学べる」状態になると、継続への抵抗感が大幅に下がります。
「やらなければならない英語」から「またやりたい英語」へ
学習スタイルに合った方法を選べると、子どもにとって英単語学習は「ドリル地獄」ではなく「自分が理解できる言葉を増やす時間」になります。
これが、苦手を作らず長く続けるための大きなポイントです。
次の章では、覚えた英単語を「忘れない知識」に変えるための定着法と、保護者がどのように関わると効果的なのかを掘り下げていきます。
覚えた単語を定着させる復習法と親の関わり方
「そのときは覚えていたのに、翌日には忘れてしまう…」という悩みは英単語学習ではとてもよくあります。しかし、忘れることは悪いことではなく、仕組みを理解して「何度も思い出すきっかけ」を作れば、記憶は定着しやすくなります。
ここでは、定着を促す方法と親の関わり方について整理します。
①「短時間×反復」が最も記憶に残りやすい
英単語の復習には、「長時間やるより、何度も思い出す反復」が効果的です。
たとえば次のような復習リズムが定着しやすくなります。
- 1日目:覚える
- 次の日:軽くチェック(言えるかどうか)
- 3日目:もう一度声に出す
- 1週間後:クイズ形式で確認
「忘れた→思い出す」過程があると、記憶は脳に定着しやすくなります。
②「言えること」を確認したあとに「書く」に進むと定着が早い
スペルをいきなり暗記しようとすると、「やっぱり英語は難しい」と感じやすくなります。
逆に、「言える単語」を「読める単語」にし、その後「書ける単語」にする流れのほうが記憶が安定します。
おすすめの確認ステップ
- 言えるか確認(口に出す)
- 読めるか確認(文字を見て声に出す)
- 短文の中で使えるか試す
- スペルチェックは最後に行う
③親は「正解を言う人」ではなく「思い出すきっかけを作る人」
復習の際に、親がすぐに答えを教えてしまうと、子どもは「考える前に頼る」習慣がついてしまいます。
定着を助けたい場合は、以下のような声かけが効果的です。
- 「ヒントあったほうがいい?」
- 「これ、走っているときの単語だったよね」
- 「この単語、前に歌の中に出てきたよ」
「思い出そうとする」行動自体が記憶の定着力を高めます。
④「できた瞬間」を記録すると学習意欲が続く
英単語が覚えられたとき、「できたね!」と声をかけるだけでなく、「英単語ノートの“できたマーク”」や「覚えた単語カードを『合格ボックス』に入れる」など、“見える積み上げ”を作ると、継続のモチベーションになります。
効果的な「積み上げの見える化」例
- 覚えた単語カードを別ボックスに分ける
- 「読めた日」「書けた日」を記録する
- 10語ごとに小さなご褒美を設定する
定着を楽しめる仕組みがあると「忘れにくい英単語」になる
復習は「やり直し」ではなく、「自分の覚えた言葉を再確認する時間」として認識できると、学習への抵抗感も減ります。
家庭での関わり方が「英単語を覚えなさい」から「どこまでできたか一緒に確認しよう」に変わることで、英語が長く続く学びになります。
次の章では、「覚えにくい」「スペルでつまずく」「単語カードで覚えても使えない」など、よくある失敗例やNGなやり方について解説し、正しい方向に修正する視点をお伝えします。
よくあるつまずきと対策|「覚えられない」「スペルが苦手」を防ぐ方法
英単語がなかなか定着しない原因は「覚える力の問題」ではなく、「覚え方が単語学習に合っていないこと」が多くあります。ここでは、小学生が特につまずきやすいケースと、その改善方法をわかりやすくまとめます。
NG①「とにかく書かせるだけの反復」が逆効果になるケース
「10回書いて覚えなさい」という方法は、意味を理解せず思考が止まってしまうため、書く作業が「ただの手の運動」に終わることがあります。
この方法で起こりがちな問題
- スペルは書けても意味が曖昧なまま
- 読み方がわからないまま書いている
- 「苦しい時間」という印象だけ残る
書く前に「音」「意味」をしっかりインプットしておくことがポイントです。
NG②「単語カードの丸暗記」で終わるタイプ
単語カードは便利な学習ツールですが、「裏の単語を当てるだけ」の形式だと、実際の会話や文章に繋がらない場合があります。
ありがちな失敗例
- カードは覚えたが、文章になると出てこない
- 意味だけ覚えて、読みや発音がわからない
- 文脈がないため、使いどころがわからない
改善策として、「単語カードを見て短文を言う」「題材ごとにグループ化する」「会話遊びに使う」など、使う前提で覚える方法が効果的です。
NG③「文法がわからないまま単語だけを増やす」
「apple」「dog」「run」など単語だけ覚え続けても、実際に使うときに「どう作文してよいかわからない」という壁に当たります。
この場合には、以下のように文の中で覚える流れが効果的です。
- I like apples. → apples, like の意味が自然に残る
- This is a dog. → dog は「~だ」となるイメージが定着
- I can run. → run が「走る」として動きと結びつく
「単語→文法」ではなく「短文→単語」の順で学習すると、英単語は使えるものになります。
NG④「間違えることを恐れて声に出さなくなる」
発音やスペルを間違えると厳しく訂正される環境は、挑戦意欲を下げ、記憶からも遠ざかります。
「英語=緊張するもの」という状態になると、単語を覚えようとしても自信が持てなくなります。
改善ポイント
- 「合っているかどうかより、言ってみたことを評価」する
- 「惜しい!」の表現で前向きな修正を促す
- 「言える単語→書ける単語」の流れを丁寧にたどる
「覚えられない」には理由がある。覚えやすい流れを作れば伸びる
英単語の定着を妨げる多くのケースは、「学び方の順番が先走ってしまっている」ことが原因です。
逆に、「音→意味→読み→文→スペル」の流れが守られていれば、自然に記憶が定着します。
次の章では、ここまでの学習段階を踏まえて、「学年別にどの程度の単語を目指せば良いのか」「無理のないステップアッププラン」を整理し、保護者が目安を持てるように解説していきます。
学年別に目標にしやすい英単語の範囲とステップアップの道筋
「小学生のうちにどれくらい単語を覚えておくべきか?」という問いに明確な正解はありません。ただし、学年ごとに「無理なく覚えやすいステップ」を知っておくことで、学習の方向が定まりやすくなります。
ここでは、学年段階に応じた「目標イメージ」と「習得につながりやすい内容」を整理します。
小学1年生〜小学2年生は「知っている英語の音」を増やす時期
この時期の目標は「書けること」ではなく、「聞いたことがある」「言ってみたことがある英単語」を少しずつ増やしていくことです。
- apple / banana / cat / dog / run / jump など
- 歌やチャンツで耳に残る表現
- “I like〜.” “Hello!” “Thank you.” といった挨拶文
目標数:10〜20語程度「自然に口に出せる単語」がある状態が理想。
関連記事
小学3年生〜小学4年生は「意味と音が結びついた単語」を増やす時期
学校の外国語活動が始まるため、「これは何の意味か?」を理解しやすくなります。この学年では、「カテゴリごとの単語学習」が効果的です。
- animals(cat / dog / bird など)
- foods(apple / bread / juice など)
- daily items(bag / pen / desk など)
目標数:30〜50語程度(文の中で出てきたら理解できるレベル)
関連記事
小学5年生〜小学6年生は「短文で使える単語」へとステップアップ
英語が教科化され、中学準備を意識し始める時期です。この段階では、「英単語単体」ではなく、「フレーズや短文の中で理解できる単語」を増やしていきます。
例)
- I like baseball.
- This is my sister.
- I can swim.
また、英検5級(300〜400語レベル)を目標にするケースも増えてきますが、全てを完璧に暗記するのではなく、「よく使うものから無理なく理解」する流れが大切です。
目標数:100語程度を「聞いて意味がわかる」状態にしておくのが望ましい目安。
関連記事
「覚えるべき語彙数」ではなく「段階に応じた理解の深さ」が重要
英単語学習は「100語覚えたら合格」ではなく、「その学年で理解しやすい学習法で意味づけができているかどうか」のほうが重要です。
- 低学年は「口に出せる」
- 中学年は「意味がわかる」
- 高学年は「短文で使える」
この流れを守れば、単語数が少なくても土台がしっかりした「伸びる学習」になります。
次の章では、「小学生の英単語学習におすすめの教材・アプリ」をタイプ別に比較しながら解説していきます。特に「どのような子に合うか」「何を目的に選ぶか」を軸に紹介していきます。
小学生の英単語学習におすすめの教材・アプリ比較
英単語学習を始めるとき、「どの教材が良いか」「アプリなら何がいいか」という質問がよく出ます。数が多すぎて迷ってしまうこともあるでしょう。ここでは、子どもの学び方タイプに分けて教材・アプリを選びやすく整理します。
タイプA:音やリズムを重視する子ども向け教材・アプリ
- 歌やチャンツを流しながら声に出すアプリ
- クイズ形式で「言える・聞ける」を重視するアプリ
- キャラクターとやり取りできるゲーム型教材
→ 音を体感して英語に親しむ段階に最適
タイプB:意味・イメージで覚えやすい子ども向け教材・アプリ
- イラスト付きカードやアニメーション教材
- カテゴリ別(food / animal / school)に整理されている教材
- 聞いて→見て→言う流れが設計されているもの
→ 音・意味・視覚を同時に刺激して記憶を強める段階で効果的
タイプC:短文や読み書きに進みたい子ども向け教材・アプリ
- 短文を音声と文字両方で学べるアプリ
- フォニックス・読み・書きを意識した教材
- 英検5級レベルを目標にしたワークブック型教材
→ 読める・書ける段階にも入り始めた子どもにおすすめ
教材・アプリを選ぶときに確認したい3つの視点
- 音声がきちんと付いていて、自分で声に出せる設計になっているか
- 学年やレベルに合った導入がされており、いきなり難しくないか
- 親が学習状況を確認できる仕組み(進捗表示・復習チェックなど)があるか
これらを基準に選べば、教材・アプリ選びで「失敗した」「続かなかった」という後悔を減らせます。
効果的な単語学習を習慣化するためのまとめ
小学生の英単語学習は、「どれだけ覚えたか」ではなく「どの順番で身につけたか」が定着のカギになります。本記事で紹介した内容を、次の流れとしてイメージしてもらえると理解しやすくなります。
小学生の英単語学習ステップ
- 音で聞く・口に出してみる
- 意味をイメージと言葉で理解する
- 短文や会話の中で使ってみる
- 読めるようにする(音と文字の結びつき)
- 書けるようにする(定着の仕上げ)
覚えられない原因になりやすいNG行動
- 書くことから始めてしまう
- 単語カードだけで丸暗記しようとする
- 意味と音が結びつく前に暗記を急ぐ
- 間違いを指摘しすぎて口を閉ざしてしまう
定着を強める工夫
- 短くても声に出す習慣をつける
- 3日後・1週間後など軽い復習を入れる
- 「できた単語」を見える形で記録する
- 保護者は「思い出すきっかけ役」になる
学年ごとの目標イメージ
| 学年 | 目標感 |
| 小1〜2 | 音として知っている英単語を増やす |
| 小3〜4 | カテゴリごとに「意味のわかる単語」を増やす |
| 小5〜6 | 短い文の中で単語を使えるようにする |
英単語学習を「やらなければならないもの」として与えるのではなく、「使えることが増える学び」として経験していくことで、英語は“苦手になりにくい教科”になります。
最後に
「覚えること」をゴールにするのではなく、「自分で言える」「読める」「意味がわかる」体験を積み重ねることが、自然な学びの流れを作ります。
英単語を覚える方法はひとつではありませんが、「その子に合った覚え方」を早い段階で見つけられると、中学以降の伸び方にも大きな差がつきます。
もし、「うちの子にはどの覚え方が合うんだろう?」「覚えてもすぐ忘れるのはなぜ?」と感じられたら、一度お気軽にご相談ください。
インスパイアスクールでは、
- 音から入るタイプ
- イメージで理解するタイプ
- 文で覚えやすいタイプ など、
お子さまの特性に合わせた“英単語の身につけ方”を提案しながら学習を進めていきます。
「まずはうちの子に合った覚え方を知りたい」という方も大歓迎です。
初めての体験授業では「どう覚えると楽になるのか」を体感できるよう、わかりやすいステップで学びます。
まずは無料体験から始めませんか?

お子様の「勉強が苦手」を「楽しい!」に変える第一歩です。
柔軟な年頃のお子さんをお持ちのお母様、お子さんの可能性を広げるキッカケを見つけてみませんか?お気軽にお問い合わせください。
お子さんの状態に寄り添って学びの土台を育んでいきますので、定員に達ししだい受付を終了させて頂きます。あらかじめご了承ください。
よくあるご質問
-
小学生が英単語を覚えるのは早すぎませんか?
-
英単語学習といっても、低学年のうちは「書くこと」ではなく「音で知っていること」から始める流れが基本です。「apple=あの赤い果物」「run=走るイメージ」といった感覚を早めに持っておくことで、中学以降の学習がスムーズになりますので、決して早すぎることはありません。
-
書いても覚えられない場合、どうすれば良いですか?
-
「文字から覚える」のではなく「言える→意味がわかる→読める→書ける」の順番で進めることで記憶が安定します。特に“言える単語”は書きやすく、“意味と音がわかっている単語”ほど定着しやすくなります。
-
覚えてもすぐ忘れてしまいます。原因は何ですか?
-
1回で覚えようとするため、記憶が短期記憶で終わってしまうケースが多いです。1日後・3日後・1週間後と「短い復習」を入れるだけで忘れにくくなります。また“文の中で使った単語”のほうが記憶に残りやすい傾向にあります。
-
低学年のうちからスペルを覚える必要はありますか?
-
低学年ではスペルを正確に書けることよりも「英単語の音と意味が結びついているか」のほうが重要です。スペル練習は、中学年以降「読み方と結びついた」段階で取り入れたほうが自然に定着します。
-
英検対策はいつから始めるのが良いですか?
-
英検5級レベルであれば、小5~小6で挑戦するケースが増えています。ただし、受験を目的に学習を詰め込むのではなく、「英単語やフレーズを“使えるもの”として理解できているか」を基準に進めることが大切です。
-
体験授業ではどんな覚え方が学べますか?
-
お子さまのタイプを確認しながら、「音から覚えるタイプ」「イメージで覚えるタイプ」「文で覚えるタイプ」などに合わせた学習方法を体験できます。「なぜ覚えやすいのか」「どうすると忘れにくいか」を感じ取れるような内容になっています。
-
家庭ではどのくらい英単語の練習をすれば良いですか?
-
長時間よりも「1日5~10分を短く楽しみながら」が効果的です。「昨日覚えた英単語を言ってみる」「小テスト風にクイズを出す」「親子で短文を言い合う」など、生活の中に自然に取り入れることが長続きのポイントです。
まずは無料体験から始めませんか?

お子様の「勉強が苦手」を「楽しい!」に変える第一歩です。
柔軟な年頃のお子さんをお持ちのお母様、お子さんの可能性を広げるキッカケを見つけてみませんか?お気軽にお問い合わせください。
お子さんの状態に寄り添って学びの土台を育んでいきますので、定員に達ししだい受付を終了させて頂きます。あらかじめご了承ください。