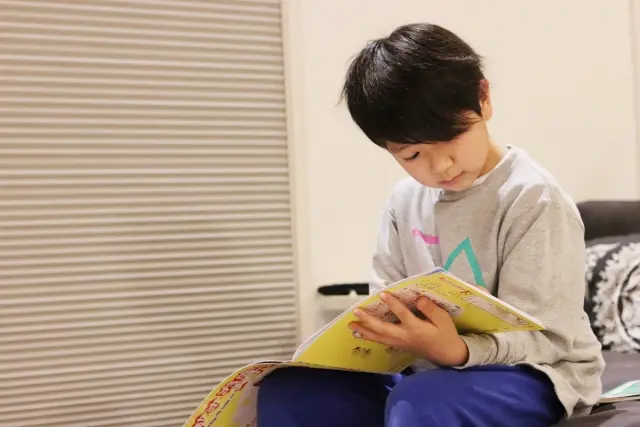
- 「小学生の英語学習って、いつから始めたらいいの?」
- 「学校の授業だけで大丈夫?」
- 「自宅学習と塾、どっちがいいんだろう…」
このように、英語教育の早期化が進む中で、不安を感じている保護者の方は少なくありません。
2020年から小学校の英語教育は大きく変わり、3・4年生で“外国語活動”、5・6年生では成績がつく“教科”として英語が扱われるようになりました。
しかし、子どもによって理解度の差が広がりやすく、「英語がわからない…」と早い段階で苦手意識を持ってしまうケースもあります。 そこで本記事では、小学生の英語勉強について次のポイントをわかりやすく解説します。
- 英語はいつから始めると効果的?
- 小学校の授業内容とその狙い
- 学年別に最適な英語勉強法
- 自宅学習・塾・オンライン英語のメリットと違い
- 英語嫌いにしないための親のサポート方法
この記事を読むことで、お子さまに合った英語学習の始め方と、無理なく英語力を伸ばすための環境づくりが具体的にイメージできるようになります。
それでは、まずは「英語はいつから始めると良いのか?」という疑問から見ていきましょう。
小学生の英語学習はいつから始めるべきか?現状と課題を整理
「早く始めたほうが良い」と聞く一方で、「読み書きがまだなのに大丈夫?」と心配になりますよね。
結論から言うと、“耳・口を使う遊び感覚の英語”は早く、“読み書き(文字)”は段階を踏んででOKです。
無理に前倒しするより、年齢に合った入り方を選ぶことがいちばんの近道です。
いつから始める?3つの入り口
- 低学年(小1–小2):リズム・歌・チャンツ・簡単な表現(Hi, Thank you など)。
文字は“見せるだけ”で十分。耳→口を育てる時期です。 - 中学年(小3–小4):学校で「外国語活動」が始まる学年。
音と意味の結びつき+フォニックスの入口(音と文字の対応)を少しずつ。 - 高学年(小5–小6):英語が“教科”として評価される学年。
短い語句→簡単な文へ。音読・シャドーイング・書く練習を小ステップで。
目安は「短く、毎日か2日に1回」。
たとえば 15分×週3〜5回。長時間の詰め込みより、薄く長くが効果的です。
学校の現状:聞く・話すが中心 → 高学年で読み書きが増える
学校の現状:聞く・話すが中心 → 高学年で読み書きが増える
2020年の学習指導の変化で、低・中学年は音声中心、高学年で読み書きが増加。
この段差で、
- 音は拾えるのに文字でつまずく
- 単語暗記が中心になり苦手意識が芽生える
- 発音に自信がなく発話をためらう
といったギャップが出やすくなりました。
つまずきやすいポイント(早めに手当て)
- アルファベットの形と音が曖昧(b/d, p/q などの取り違え)
- フォニックス不在で「読めない → 書けない → 嫌い」の連鎖
- 丸暗記のみで意味が定着しない(使う場がない)
- ”間違うのが恥ずかしい”で口が開かない
→ 対策は 「音→口→目→手」(聞く→話す→読む→書く)の順を守ること。
いきなり書かせず、声に出して言える表現だけを書かせる、がコツです。
家庭で今日からできること(5分メニュー)
- 音のシャワー:好きな歌・チャンツを1曲だけ固定して毎日1回。
- まねっこ読み:短いフレーズを親子でリピート(I like … / This is …)。
- “見て書く”前の“言って指さす”:絵カードや家の物を指して英語で一言。
- 小テストは“口頭”から:声で言えたら、次にノートへ。
はじめどきチェックリスト(3つ以上当てはまれば今が好機)
- 英語の歌や動画に自分から反応する
- カタカナ英語のまねっこが楽しそう
- アルファベットに興味を示す(看板や本の文字を聞いてくる)
- 日本語の音読がスムーズになってきた
- 1日15分の机に向かう習慣がある/作れそう
小学校で行われている英語授業の内容と変化
「英語の授業が始まったのは知っているけれど、どんな内容を学んでいるのかはよくわからない…」という声はとても多く聞かれます。まずは、小学校の英語教育がどのように変わったのかを整理しておきましょう。
2020年以降、小学校の英語は「正式な教科」へ
2020年度、学習指導要領の改定によって英語教育は大きく変わりました。これまでは中学校から始まっていた英語が、小学校5・6年生では「教科」として正式に評価されるようになりました。つまり、通知表にも英語の成績がつくようになったということです。
これにより、
- 「とりあえず親しむ」から
- 「学力として評価される対象」
へと変化したと言えます。
「外国語活動」と「英語(教科)」はどう違うの?
混乱しやすい用語がこの2つです。
| 学年 | 呼ばれ方 | 学ぶ内容 | 評価 |
| 小3〜小4 | 外国語活動 | 挨拶・簡単な表現・英語に慣れる | 評価なし |
| 小5〜小6 | 英語(教科) | アルファベット・意味理解・短文 | 成績評価あり |
「外国語活動」は、英語というよりも“外国語に耳を慣らし、表現する楽しさを知る授業”。
一方、「英語(教科)」になると、「読む・書く」「理解する」「伝える」力が求められるようになります。
なぜ「聞く→話す」から始めるのか?
家庭によっては「まずは単語を覚えさせたい」「書かせたほうが身につくのでは?」と感じることもあるでしょう。しかし、言語の定着は「耳→口→目→手」の順番が自然です。
この順番を無視して「書く」から始めると、カタカナ発音や丸暗記に偏り、後からつまずきやすくなります。 学校の授業が「音声中心」なのは、この言語習得プロセスに沿っているためです。
授業だけでは補いにくいギャップとは?
もちろん学校でも工夫された授業が行われています。しかし、次のような課題も指摘されています。
| よくある課題 | 原因となりやすい実態 |
| 言ったことはあるが、文字にできない | 音と文字がつながらない |
| 単語は読めるけれど意味が曖昧 | 丸暗記に寄りがち |
| 「英語=苦手」と早期に決めつける | 成功体験の不足 |
| 発音を恥ずかしがって発話できない | “間違い=恥”という意識 |
特に、「高学年から読み書きが一気に増える」ことが大きな負担になるケースが多く見られます。
だからこそ、家庭では
- 「授業内容の理解を支える」
- 「無理なく声に出せる雰囲気を作る」
- 「成功体験を積むきっかけを与える」
というサポートが重要です。
学年別|小学生に合った英語勉強法と押さえるべきポイント
「小学生の英語」と一言でいっても、小1と小6では理解の仕方も集中力もまったく違います。ここでは“学年によって伸びる力・つまずきやすいポイント”を整理しながら、英語勉強法を段階的に解説していきます。
小学1年生〜小学2年生は「まねして言える」経験を増やす時期
低学年の子どもにとって、「楽しい」「リズムが心地いい」「つい口ずさむ」という感覚は学習の入口になります。
この段階で必要なのは「書けるようにさせること」ではなく、“英語の音と仲良くなる”ことです。
おすすめの学び方
| 方法 | ポイント |
| 歌・チャンツ | 毎日同じ曲を流すだけでもOK |
| まねっこフレーズ(Hi! / Thank you) | 使えた瞬間をほめる |
| 英単語カード遊び | 発音よりも「楽しさ」重視 |
NG例
「アルファベット全部を無理に書かせようとする」→苦手意識の導火線に。
小学1年生・小学2年生の関連記事
小学3年生〜小学4年生は|「音と意味をつなげる」ステップ期
この学年から学校で外国語活動が始まるため、「聞く→話す」に加え、「意味がわかる」「リズムに乗って表現できる」段階へ進めやすくなります。
この時期に意識したいこと
- よく使う表現(I like ~/This is ~)を「自分ごと化」
- フォニックスで“読めそう感”を育てる
- 「発音→文字」の流れを少しずつ入れる
たとえば「cat」「dog」など、言えてから読む→書くの順に進むと自然です。
小学3年生から小学4年生の関連記事
小学5年生〜小学6年生は「自分の言葉で伝える」力を育てる時期
英語が教科化され、「読む・書く・話す・聞く」の4技能が求められていくステージです。この段階で、「英語が楽しい」状態か「よくわからなくて苦手…」なのか、大きく分かれます。
勉強を定着させるためのポイント
| ポイント | 理由 |
| 「音読・シャドーイング」を取り入れる | 発音→リズム→意味がつながる |
| 短文の穴埋めや並べ替え | 書く前の定着チェックに◎ |
| 英検5級・4級を目標に | モチベーションになりやすい |
留意点
この時期からは「書ける」が「話せる」につながりやすくなります。
小学5年生から小学6年生の関連記事
どの学年にも共通する“押さえるべき1つの鉄則”
「言えないものは書けない」
このシンプルな原則を大切にすることで、無理のない進み方ができます。逆に、文字だけで覚えようとすると、苦手意識につながりやすくなります。
自宅学習と塾・オンライン英語学習のメリット比較
「小学生の英語学習は家庭でもできるのか」「塾に通わせたほうが良いのか」「オンライン英会話も気になる」など、学びの方法を決める段階で迷う保護者は少なくありません。
それぞれにメリットや向いているタイプがあるため、比較しながら考えると判断しやすくなります。
自宅学習|「気軽に始めやすい」が「続ける仕組み」がカギ
市販の英語教材や動画、アプリなどを使えば、家庭でも英語学習を始めることはできます。特に低学年のうちは「遊びの延長で英語に触れられる」という点が大きなメリットです。
ただし、家庭学習で陥りやすい課題が「だんだんやらなくなる」という継続の壁です。
学習管理をすべて家庭で行う必要があるため、親のサポート負担が高学年になるにつれて大きくなりやすい点にも注意が必要です。
オンライン英語学習|「話す力」を伸ばしやすいが、目的に合った選び方が重要
近年増えているのが、マンツーマンで英語を話せるオンライン英会話サービスです。英語の「音」をリアルに使う環境が手軽に手に入るのが最大の特長です。
英語に対する抵抗感が少ない子どもや、発話を楽しめるタイプの子に向いています。
ただし、「英語を話す場」としての効果は大きい一方で、基礎力が身についていない場合、レッスン内容が流れてしまうことがあります。文の型や語彙が身につく学習体系が用意されていない場合、伸びが不安定になることもあります。
学習塾|「理解の積み上げ」「読める・書ける」につなげやすい環境
塾で学ぶ最大の強みは、「学ぶ順番」が整理されていることです。音から入り、語彙を定着させ、読み書きへ進むという英語習得の流れが組まれていれば、自宅学習で生じがちな「できるようになっているのかわからない」という不安も軽減されます。
また、学習の進捗管理やモチベーション維持を講師がサポートするため、一人では続けられない子にも向いています。
特に高学年では「学校の授業についていけているか」「中学英語への準備ができているか」をチェックしながら学べる点が大きな安心材料になります。
どの方法が向いているのかは「学習目的」と「性格のタイプ」で変わる
| 学び方 | 向いているタイプ |
| 自宅学習 | 好奇心が強く、自分で楽しく進められる子 |
| オンライン英語 | 英語を話すことが好きで、臆せず発話できる子 |
| 塾 | 学習の流れを整理してほしい子、読み書きも強化したい子 |
いずれの方法を選ぶ場合でも、重要なのは「なんとなく続ける学習」ではなく、「目的につながるステップがあるかどうか」です。
英語が苦手にならないために|親ができるサポートの考え方
小学生の英語学習の成功は、教材や学習方法だけで決まるものではありません。むしろ「英語にどう向き合うか」「気持ちの状態をどう支えるか」という点が大切です。特に高学年になるほど、自信の有無が習得スピードに影響しやすくなります。
ここでは「親が頑張らせる」のではなく、「英語へのハードルを下げる」という視点でサポートのポイントを整理します。
いきなり成果を求めず、「できた瞬間」を見逃さない
英語は成果がすぐに目に見えにくいため、焦りから「書けた?」「覚えた?」とチェック項目で測ろうとしてしまいがちです。
しかし、小学生のうちは「知っている」「言ってみた」「なんとなく理解できた」といった小さなステップが成長の種になります。
たとえば、次のような反応は十分に成長のサインになります。
- 「これ英語で●●って言うんだよね」と口にした
- 動画を見ながら英語の音をまねしようとした
- 正しい発音ではなくても、リズムを掴んでいる
こういった小さな前進をキャッチして「今のいいね」と言葉にすることで、学習に対する安心感が高まります。
「間違えること=恥ずかしい」を崩してあげる
英語を声に出すことをためらう子どもは少なくありません。特に完璧主義のタイプや、周りの反応を気にしやすい性格の子は「発音が違っていたらどうしよう」という不安から黙り込んでしまうことがあります。
そんなときは以下のような言葉が効果的です。
- 「英語は間違いながら覚えるものだよ」
- 「正解よりも、言ってみようとしたことがすごい」
- 「先生たちも間違えながら話せるようになったんだよ」
失敗を責めない雰囲気は、挑戦を促す土台になります。
「やらせる」より「一緒に始める」
家庭学習の場合、低学年ほど「一人でやってきて」よりも「ちょっと一緒に歌聞こうか」「この単語、どっちが早く言えるか勝負しよう」という軽い誘いから始めるほうがスムーズです。
たとえば次のようなスタイルは続けやすくなります。
- 親子でチャンツを聞きながらリズム遊び
- 「この単語、どんな意味っぽい?」とあてっこ
- 音声に合わせて口パクだけ一緒にやってみる
無理に机に座らせるのではなく、「英語がある生活」に自然と触れさせることがポイントです。
「目的」を見える形にしておくと継続につながる
高学年になると「なぜ英語を学ぶのか」という目的を少しずつ伝えていくことも大切です。
- 中学英語でスタートからつまずかないため
- 英検合格が自信につながるため
- 「話せるようになりたい」という自己表現につながるため
目的がわかると、学習を「やらされること」から「やる理由があること」へ変えることができます。
小学生に人気の英語学習教材・アプリ・プリントの活用法
英語学習を始めるとき、まず検討されやすいのが「教材・アプリ・プリント」です。
ただし「人気だから」「楽しそうだから」という理由だけで選ぶと、学年や目的に合わず、長続きしないケースがよくあります。ここでは、活用しやすさと習得の流れに沿った形で、3つの学習タイプに分けて整理してみます。
耳と口を育てる「リズム型アプリ・映像教材」
低学年や、まだ読み書きに入る前の段階で効果的なのが「音とリズムから英語に触れるタイプ」の教材です。
このタイプは学習というより「なじむ」ステップとして活用できるため、英語への抵抗感を減らす入り口になります。
- 英語の歌やチャンツ(歌詞を覚えさせる必要はない)
- リピート型アプリ(音をマネするだけで良いもの)
- キャラクターと会話形式で楽しめる教材
ポイントは「正確さを求めすぎないこと」です。音を楽しむところから始めると、次のステップにスムーズにつながります。
フォニックスや短文につなげやすい「ステップ型教材」
英語を「読む」「理解する」学習に入るタイミングで取り入れたいのが、学習の流れが整理されているステップ型教材です。単語や文型をスモールステップで積み重ねることで、「英語は難しい」という壁を感じにくくなります。
- アルファベット→フォニックス→単語→短文へと進む教材
- 音声と文字がリンクしているもの(聞いて→言って→読む)
- 「書く前に声に出す流れ」が組まれているもの
このタイプは、高学年や英検5級・4級を目指す段階でも活用しやすくなります。
自信を定着に変える「問題演習型・プリント教材」
ある程度表現が口から出るようになってきたら、「読める・書ける」を仕上げていくステージに移ります。この段階で単語穴埋めや並べ替えプリントなどを取り入れると、理解と記憶の定着が深まります。
- 簡単な単語テスト(言える表現だけを書く)
- 短文の並べ替え
- イラストのあるプリントで意味を再確認
ただし、いきなり「書くことが目的」になると、英語への苦手意識につながることもあるため、「言えてから書く」順番を守ることが重要です。
大切なのは「順番」と「今のレベルにぴったり合うか」
教材がどれだけ評判でも、以下のいずれかにあてはまると続きにくくなります。
- 音声中心の段階なのに書くことが中心になっている
- 英語を話し始めたばかりなのに文章理解に進んでしまう
- モチベーションタイプと教材の雰囲気が合っていない
逆に「少し背伸びすれば届くレベル」を選べると、学習は自然に継続しやすくなります。
英語学習で失敗しないための注意点とよくあるNG例
小学生の英語学習では、学習内容そのものよりも「進め方のミス」によってつまずくケースが少なくありません。特に、親の「早くできるようになってほしい」という期待や、焦りからくる指導が逆効果になることがあります。
ここでは、つまずきを防ぐために意識しておきたいポイントと、避けたいNG例をいくつか紹介します。
NG①「書くことを先にやらせようとする」
「アルファベットを全部書けるようにさせたい」「単語も書かせて覚えたほうがよいのでは?」と考える保護者は少なくありません。しかし、音が定着していない状態で書く作業から始めると、次のような状態につながりやすくなります。
- 発音と文字の結びつきが曖昧なまま暗記に進む
- 「書くこと=英語学習」と思い込み、苦手意識につながる
- フォニックスの順序を無視してしまうことで混乱する 英
英語は「言えないものは書けない」ため、書く練習をする前に「口に出して言える状態」をきちんと作ることが大切です。
NG②「丸暗記頼りで“意味のない暗唱”にしてしまう」
英語を声に出して読むこと自体はよい習慣ですが、内容の理解を伴わない暗唱だけを繰り返していると、次の段階に進みにくくなります。
- 日本語訳がわからず、音を追っているだけ
- 応用がきかず、似たパターンが出ると理解できない
- 「覚えられない」という失敗の積み重ねで苦手に感じる
暗唱は「意味が理解できて」「表現として使える」段階で行うと、自分の言葉として定着しやすくなります。
NG③「難しい内容に急に飛び込ませる」
特に高学年でありがちなのが、英検対策や中学範囲に急に取り組んでしまうケースです。本人の「できそう」という感覚よりも「難しい」という気持ちが勝ってしまうと、その時点で学習意欲が落ちてしまいます。
見極めのポイントは次の通りです。
- 意味がわかる単語が文の半分以上あるか
- 声に出したときにストレスなく言えるか
- 少し考えれば理解できるレベルか
「少し背伸びすれば届くレベル」を選ぶことで、成功体験とともに伸びる感覚を得られます。
NG④「間違いに敏感になりすぎる」
英語学習では「言い間違える」「発音を崩す」といったことは自然な過程です。しかし、「違うよ」「そうじゃない」といった否定的な指摘が続くと、発話すること自体を避けるようになってしまいます。
間違いを「失敗ではなく“次のヒント”」として受け止められる空気づくりが、長期的な学習継続につながります。
「完璧よりも“続けられる方法”」を選ぶことが成功の第一歩
失敗を防ぐ最大のポイントは、正確さではなく「英語のある生活を無理なく継続できること」を優先する姿勢です。
特に小学生の段階では「継続できる」「少しずつできることが増える」という感覚が定着の核になります。
小学生のうちに英語力を高めることで得られる将来のメリット
小学生の英語学習は、中学の準備だけではありません。早い段階で「英語を理解できる感覚」「英語に向かう抵抗のなさ」を身につけておくことで、将来の学力面・心理面・選択肢の面で大きな差につながります。
ここでは、小学生から英語に触れておくことによって得られる主なメリットを整理してみましょう。
中学1年のスタートで「つまずかない」
中学校の英語は、授業スピードが速く、少しでも理解が遅れると「最初の1年間で苦手になる」というケースがよく見られます。
逆に、小学生のうちに英語に慣れておくと:
- 授業のスピードにおびえない
- 文型や単語への理解がスムーズ
- 発音への抵抗が少ないため、発話にも積極的になれる
「わからない」状態で中学に入るのと、「知っている表現がある状態」で入るのとでは、学び始めの心理的な負担が大きく異なります。
「英語が苦手」になる前に「少しわかる」を積み重ねられる
英語への苦手意識は、「知らない」からではなく、「できない経験が続いた」ことで生まれます。
そのため、小学生のうちに「言える表現がある」「聞き取れる単語がある」という小さな成功を積み重ねた子どもは、英語に対する自信を持ちやすくなります。
「英語=暗記」ではなく「使えるもの」として定着しやすい
小学生のタイミングで音・リズムを通して英語に親しんでおくと、「英語は覚えるもの」ではなく「使うもの」という感覚が早い段階で自然に身につきます。
そこから「伝える楽しさ」「表現できる嬉しさ」につながり、「習う科目」より「自分を広げる道具」として捉えられるようになります。
英検などの資格に挑戦しやすくなる
英語が教科化される高学年以降は、「目標があるほうが伸びやすい」という子どもも増えてきます。その際、「英検5級・4級」などの資格試験が明確な目安になります。
英検合格は、
- 「できた」という達成感
- 「次もやってみよう」という意欲
- 通知表や中学受験へのプラス要素
といった役割を持ち、学習の軸になりやすいステップです。
「自分で表現できる言葉」を増やすことは、将来の選択肢への広がりにつながる
英語学習の目的は、単なる成績向上だけではありません。将来的に好きなことに挑戦する際、英語ができるかどうかで選べる選択肢が増えることも確かです。
- 海外の情報を自分で読める
- 好きな分野の動画学習が英語でできる
- 将来の職業選択の幅が広がる
「勉強のための英語」ではなく、「生き方を広げる英語」として考えることで、学習の価値がより実感しやすくなります。
まとめ|英語学習を好きなまま伸ばす環境づくりが成功の鍵
小学生の英語学習は「いつから始めるか」よりも、「どのような順番で、どんな気持ちで続けられるか」が大切です。
特に、音で楽しむ時期、意味を理解する時期、読み書きを安定させる時期という流れを自然に踏めると、英語を無理なく「自分の言葉」として受け入れやすくなります。
学習を成功に導くためのポイントをまとめると、次のようになります。
- 低学年は「音・リズム」と「まねっこ」から始める
- 中学年では「意味がわかる」「言えてから読む」流れを作る
- 高学年では「短文の理解」「書ける→使える」に段階を進める
- 家庭学習・オンライン・塾などの方法は「学び方に合うか」で判断する
- 結果を急がず、できた瞬間を認める習慣が学習意欲につながる
- 英語学習は“勉強”ではなく“世界と出会う手段”として意識づけると続きやすい
「小学生 英語 勉強」で検索する保護者の多くは、「正しいスタートの切り方」を探しています。しかし、完璧な方法は最初から決める必要はありません。むしろ、小さな成功体験を積みながら、学びやすいスタイルを見つけていく姿勢が、苦手意識を遠ざけ、得意分野へと育てていく一歩になります。
もし、お子さまの学習ペースや性格に合わせた指導スタイルを見つけたい、家庭学習が難しいと感じている、英検対策や中学準備を見据えたいという場合には、体系的に学べる環境を選ぶことも1つの選択肢となります。
小学生の英語学習を進めるうえで大切なのは、“がんばらせること”ではなく“自分で理解できる楽しさを感じられること”です。
もし「うちの子にはどんな進め方が合うんだろう?」「自宅学習だけで大丈夫か不安」と感じられたら、一度お気軽にご相談ください。
当サイトのインスパイアスクールでは、
- 英語が初めてでも「話せた!」を実感しやすい授業設計
- 学年や性格に合わせた学習ステップの提案
- 英検対策や中学英語への準備にもつながる指導
を通じて、「自分の力でわかる」「使える英語」を身につけられる環境を整えています。
英語を好きなまま伸ばしてあげたいと思われた方は、まずは体験授業からスタートしてみてください。
お子さまの様子を見ながら、一人ひとりに合った学び方をご提案いたします。
まずは無料体験から始めませんか?

お子様の「勉強が苦手」を「楽しい!」に変える第一歩です。
柔軟な年頃のお子さんをお持ちのお母様、お子さんの可能性を広げるキッカケを見つけてみませんか?お気軽にお問い合わせください。
お子さんの状態に寄り添って学びの土台を育んでいきますので、定員に達ししだい受付を終了させて頂きます。あらかじめご了承ください。


